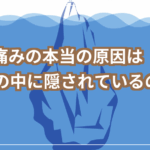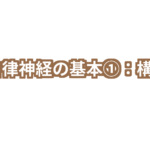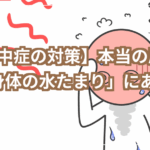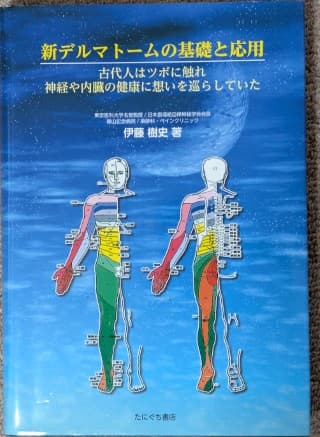はじめに:身体の「認知力」を高める旅へ
第1部では、自律神経というシステムの、精緻な「設計図」についてお話ししました。
この記事では、いよいよ「なぜ、その設計図がうまく機能しなくなるのか」という、あなたの不調の核心に迫っていきます。その鍵を握るのが、「認知」という言葉です。
痛みは、押したり動かしたりすることで、初めて脳が「そこに問題がある」と認知できます。押した時の痛み(圧痛)は知覚、動かした時の感覚は感覚。この2つを正しく使うことで、脳は身体の状態を正確に把握し、治癒のための適切な指令を送ることができるのです。
しかし、もし身体に脳が認知できない「無意識な部位」があったとしたら? 脳は、そこに異常があることは感知しても、何が異常なのかは分かりません。その結果、例えば血圧を上げ続けたり、常に身体を緊張させたりといった、「間違った指令」を送り続けてしまうのです。
部位別の働きと、不調のサイン
脳神経の悲鳴:夜になるとお腹が張る、その理由
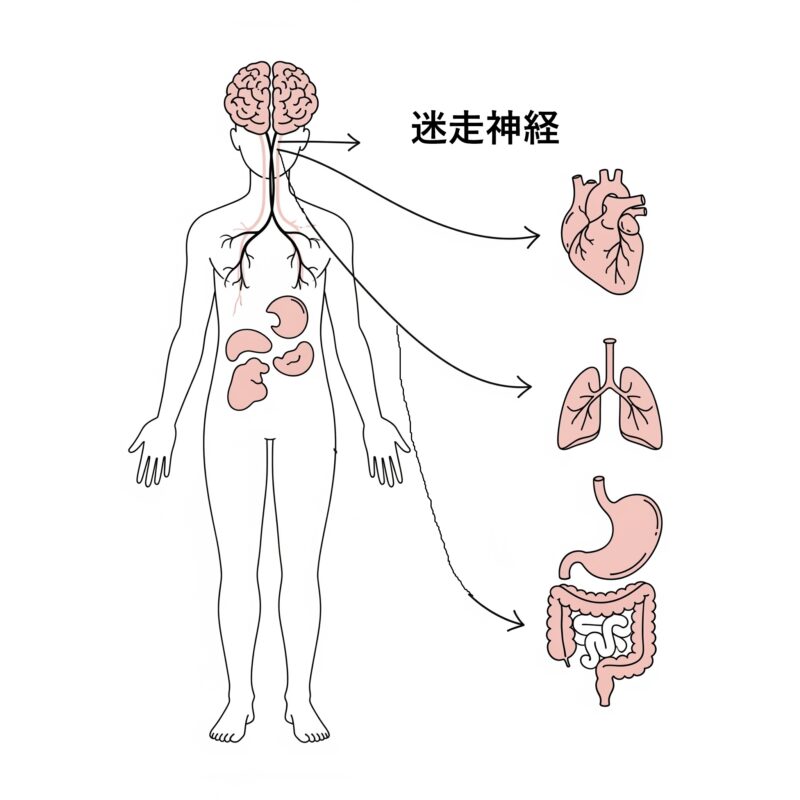
私たちの胃腸の働きは、主に脳神経の一つである迷走神経(副交感神経)がコントロールしています。日中、活動している時(交感神経優位)は消化活動を抑え、夜、リラックスしている時(副交感神経優位)に活発に動くように設計されています。
しかし、首の歪みなどで迷走神経の働きが乱れると、この切り替えスイッチがうまく機能しなくなります。夜になっても胃腸が休息モードに入れず、消化不良を起こし、ガスが溜まる。これが、「夜になるとお腹が張る」という不調の正体です。
脊髄神経の悲鳴:熱中症になりやすい人の、背中のサイン
脊髄から出る自律神経は、全身の血管の収縮や発汗をコントロールしています。
しかし、背骨に歪みがあったり、その周辺に「むくみ」があると、その部位の神経機能は低下します。そのサインは、色素沈着、くすんだ皮膚、圧痛といった形で、皮膚表面に現れることが少なくありません。
脳がその部位を正しく認知できないため、「汗をかけ」という指令が出せなくなり、熱がこもってしまう。これが、熱中症になりやすい身体環境を作り出してしまうのです。
なぜ、司令塔は間違えるのか?
なぜ「むくみ」や「冷え」があると、脳は正しく「認知」できないのか?
答えは簡単です。そこに「水たまり」があり、その淀んだ水の中の状態を、脳は正確に把握できないからです。神経伝達は微弱な電気信号であり、水は電気の流れを妨げます。これにより、脳と身体の間のコミュニケーションに、ノイズが生じてしまうのです。
Q. 脳が間違った指令を出すと、どうなるのか?
A. 身体は、様々な不調を引き起こします。
- 下肢の循環障害を「何らかの異常」としか認知できず、全身の血圧を上げて対処しようとする。
- 胃腸の働きが悪く、エネルギーが不足していると誤認し、血糖値を上げて補おうとする。
- 末端の冷えを改善するため、全身の筋肉を緊張させて熱を生み出そうとし、結果として不眠になる。
このように、普段の痛みや不調のほとんどは、自律神経の乱れという文脈で説明が可能です。
ストレスの真実:身体が先か、心が先か
「胃がキリキリする時に、心に余裕がなくなる」という経験は、誰にでもあるはずです。
精神的なストレスが胃腸の働きを低下させることもありますが、逆もまた真なり。消化・吸収・代謝という身体の基本的な機能に問題があると、身体は常にストレスを感じ、その結果、精神的にも余裕がなくなってしまうのです。
大切なのは、ストレスに強いか弱いか、ではありません。ストレスに強い、しなやかな「身体」であるかどうかなのです。
まとめ:探求の旅は、ここから始まる
この記事を通して、あなたの「原因不明の不調」が、実は身体からの具体的なサインであったことが、少しでも伝われば幸いです。
この「働き」を理解したことは、ゴールではなく、ご自身の身体と対話するための、新しいスタートラインです。ここから、さらに探求の旅を続けてみてください。
【本質的な原因を探る】 なぜ、身体の歪みがストレスに先立つのか?その根本的な哲学に迫ります。
【具体的な症状から理解する】 自律神経の乱れが、実際にどのような症状として現れるのか、具体的な事例を見ていきましょう。